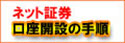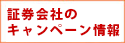株の買い方・売り方でよくある質問
株の買い方・売り方に関するよくある質問をまとめました。
基本的な手順ややり方は株の買い方と株の売り方のページに解説しています。また、株を買うときの発注画面に出てくる用語の意味は別ページにまとめました。
それ以外の買い方・売り方に関するよくある質問です。
- 買い方のコツはありますか?
- 手数料はいくらかかりますか?
- 株が買える時間や期間はいつからいつまで?
- 現物取引と信用取引の違いは何?
- 年齢は何歳から株を買うことができますか?
- ドルコスト平均法って何ですか?
- 操作が難しそうで不安ですが大丈夫?
買い方のコツはありますか?
株で利益を上げるためには「安く買って高く売る」こと、つまり買うタイミングや売るタイミングが大事です。
まずはちゃんと基本的な注文方法などのルールを理解したうえで株価チャートを見る、買う銘柄の動きのパターンをつかむなどして自分なりの勝ちパターンを見つけるのがコツです。
手数料はいくらかかりますか?
手数料は証券会社やネット証券によって違いますし、同じ証券会社でも買う金額によって手数料が違ってきます。
詳しくは証券会社の手数料比較ページを参照にしてください。
中には手数料無料で買える証券会社もあります。
株が買える時間や期間はいつからいつまで?
株が買える時間は平日の以下の時間帯です。
- 平日の朝9時〜11時半(前場)
- 平日の12時半〜15時(後場)
この時間以外にも注文を出しておくことはできますが、実際に取引がされるのはこの時間になります。
また、PTSという時間外取引で夜間に取引ができるネット証券もあります。
土日祝日は休みで年末年始は休みになります。大納会(土日祝日が重ならなければ12月30日)がその年の最後の取引日、大発会(土日祝日が重ならなければ1月4日)がその年の初めの取引日になります。
現物取引と信用取引の違いは何?
株を買うときに「現物」と「信用」というマークが出ている証券会社が多く、初心者の方は迷うこともあるかもしれません。
現物というのは現物取引(げんぶつとりひき)のことで、ようするに普通に株を買うことです。基本的に初心者の方が株を買うときはこの現物取引をします。
信用というのは信用取引のことで、証券会社からお金を借りて株を買ったり、証券会社から株を借りて売る(空売り)というものです。
自分の資金以上の取引ができるというメリットがありますが、その分リスクも高くなるので初心者のうちはまずは現物取引で慣れましょう。
信用取引をするには普通の口座開設の後に信用取引口座の開設をしなければいけないので、基本的には気にすることはありません。信用取引をする時が来るまでは「現物取引をしておけばいい」と思っていて問題ないです。
年齢は何歳から株を買うことができますか?
株を買うのに年齢制限はありません。証券口座さえ作れば0歳の赤ちゃんでも株を買うことができますし、昔から株取引をしている子供もたくさんいます。
今は未成年でも口座開設ができる証券会社はたくさんあるので、選択肢もたくさんあります。未成年の場合は口座開設の際に「親の同意書」などが必要になります。詳しくは未成年口座の作り方を参照してください。
ドルコスト平均法って何ですか?
ドルコスト平均法は、株などを買うときの買い方の手法の一つです。
「定期的に一定の値段で買っていく」という方法で、毎月○万円分ずつ買っていくといったことをし時間をかけて買っていきます。
価格が安いときはたくさん購入し、逆に価格が高いときは少量しか購入しないということになるため、平均取得単価を下げる効果があります。
メリットとして高値掴みをすることがない(高いときに買ってしまうことがない)というのがありますが、デメリットとして底値で買えることもない(一番安いときに買えることはない)というものがあります。
長期投資をするときや売買のタイミングがわからないという方におすすめの買い方ですが、株を買うのに自分でドルコスト平均法で買っていくというのはかなりの資金がないとやりにくく、どちらかというと投資信託などに向いている方法です。
操作が難しそうで不安ですが大丈夫?
株を買ってみたいけど、ネット証券の画面の操作が難しそうで不安という人もいるでしょう。
その場合はサポートの利用をおすすめします。私もサポートは時々利用すますが、今はネット証券のサポートの方みんな感じが良いんですよね。特にマネックス証券はサポートの質の面ではおすすめです。
また、株式投資以前に、パソコンが苦手で操作が不安という方もいると思います。取引画面の操作方法を教えてもらってもそもそもパソコンの使い方がよくわからないから理解できない・・・そんな方もいるでしょう。
その場合もマネックス証券の口座開設をおすすめします。
マネックス証券はパソコンの使い方がわからない方のために通常のサポートとは別に専門の「パソコンサポートダイヤル」を用意しているので、パソコンの操作方法もここで無料で聞くことができます。
次のページ >> 株を買う時の言葉の意味