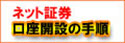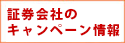つなぎ売りのやり方〜株主優待の取得に便利なクロス取引の手順

最近は株主優待をもらうために株取引を始める人も多いですね。そんな方におすすめの「つなぎ売り(クロス取引)」という方法を紹介します。
株主優待は色々な商品やサービスがもらえて嬉しいし、使い方によってはものすごくお得になる優待もあります。
しかし、株主優待で怖いのが株価が下がるリスクです。
せっかく株主優待がもらえたとしても、それ以上に株価が下がってしまって損をしてしまったのでは本末転倒です(でも私も経験あります)。しかし株なのでどうしても株価が上下するリスクはあります。
「優待はもらえたけど株価が下がって損してしまった」
なんてことは避けたいですよね。
そこでおすすめするのが、SBI証券 などを使った「つなぎ売り(クロス取引)」です。
つなぎ売り(クロス取引)のやり方を覚えれば、株価が下がる心配をせずに気持ちの余裕をもって株主優待がもらえるようになりますよ。
このページの内容
株価が下がっても損をしないで株主優待GET
「つなぎ売り(クロス取引)」という方法を使えば、株価が下がって損をしてしまうリスク無しに株主優待をもらうことができます。
つなぎ売りとは、株を買うと同時に空売りで売る、つまり、買いのポジションと売りのポジションを両方持つことで、株価が上がっても株価が下がっても影響を受けなくする方法です。
つなぎ売りをしておけば、例えば株価が100円下がってしまったとしても、空売りで100円下がった分の利益が出るので、買っていたポジションのマイナスと相殺されるということです。
その代わり、株価が上がった時にも利益は出せませんが、株価の上下で利益を上げるのではなく株主優待が目的という場合は、このつなぎ売りはとても有効です。
そう、つなぎ売りでは株主優待はちゃんともらえるんです。
株主優待だけ欲しいならつなぎ売りがおすすめ
株主優待は権利確定日に1日持ち越すだけでもらうことができます。権利確定日に買って翌日の権利落ち日に売れば1日だけの保有でも株主優待はもらえます。
しかし、そうはいっても権利落ち日(権利確定日の翌日)はみんな売るから株価が下がりがちだし、権利確定日には優待や配当狙いの人はみんな買いたいので株価が上がってしまいます。
そのため「株価が上がる前に前倒しで買っておく」といった値動きや、優待目的の買いが入るタイミングで売るなどの投資家たちの駆け引きがあります。
そこで、つなぎ売りを使えばこの値動きの心理戦に巻き込まれず、株価が上がろうが下がろうが関係なく優待をもらうことができます。
「株価がどう動くかわからない」という不安なく、計算すれば必要な資金はいくらで、コストはいくらで(手数料、貸株料、配当金の税金分)といったかかるコストと最終利益が分かった状態で株主優待がもらえます。
買うタイミングや売るタイミングを気にせず、権利付最終日に買って翌日の権利落ち日に売ればいいし、株価の値下がりを心配しなくて良いので、つなぎ売りを使うと株主優待をもらうのがすごく楽になります。
つなぎ売りのデメリット
ここで、つなぎ売りのデメリットも解説しておきます。
つなぎ売りの大きなデメリットは2つです。
- 配当金がもらえない
- 株価が上がっても利益は出ない
つなぎ売りは「株主優待をリスクなくもらう」という目的で行うので、その他のもの(配当金や株価が上がったときの利益)は無くなります。
ただ、その代わりに「優待はもらえたけど株価が下がって損をした」ということもなくなるので、優待がメインの人にはおすすめですよ。
つなぎ売りのやり方
つなぎ売りは対象の銘柄の「現物での買い」と一般信用取引を使った「空売り」を使って行います。
- 現物買い・空売りを同時に行う
- 権利落ち日まで持ち越す
- 現物買いと信用売り建玉を品渡で決済する
これだと意味がよくわかりませんね。順番に解説していきます。
1.現物買い・空売りを同時に行う
まずは株主優待を狙っている銘柄を現物で買い、同時に信用取引の売り注文で空売りをします。
このときのポイントとして、買いと売りで約定する値段が違うとそこで損益が出てしまうので、寄付前(午前9時前)に成行で注文をしておくと、その日の初値で同じ値段で約定させることができるので損益が発生しません。
また、信用取引の貸株料(株を借りるために払う利息のようなコスト)を最小限に抑えるため、権利付最終日の寄付前に買い、権利落ち日に決済してしまうことで保有期間を最短にして、貸株料を最小限に抑えます。
2.権利落ち日まで持ち越す
次に、株主優待の権利付き最終日の取引終了まで銘柄を保有します。これで株主優待の権利を取得することができました。
3.現物買いと信用売り建玉を現渡で決済する
次に、現物買いと信用売り建玉を現渡にて決済します。
現渡とは、信用取引の売り建玉を保有している現物の株式で返して決済する方法です。現渡で決済することで、決済手数料が無料になります。
文字で読むと難しく感じるかもしれませんが、1回やってみてやり方覚えてしまえばとても簡単です。とても簡単なこの方法で株価の変動リスクなく株主優待をもらうことが出来ます。
あとは株主優待の金額と取引の手数料(現物買いと信用売りの手数料、決済のときの手数料は現渡すれば無し)+貸株料(最短で2日分)を比較して株主優待の金額の方が大きければつなぎ売りをするだけです。
取引の手数料は1日100万円まで無料のところもあるので、つなぎ売りにおすすめの証券会社を参考にしてください。
株主優待のために株をやっている方は、SBI証券 や三菱UFJ eスマート証券の口座を使ってつなぎ売りをしみてください。口座開設は無料です。
つなぎ売りに必要な資金はいくら?
つなぎ売りをする時の必要資金は、「買い」と「売り」の両方のポジションを持つので2倍の資金が必要と思う人もいるようですが、基本的には100株買える金額があれば大丈夫です。(ただし、信用取引の最低保証金の30万円は必要)
50万円必要な銘柄なら、現物買いの資金50万円+信用での売りの資金も50万円、ただし信用取引は現物株を担保にできて約3倍の金額の取引ができるので実際に必要な資金は50万円で足ります。
もっと少額で買える銘柄ならもっと少ない資金で十分です。
ただし、信用取引をするために最低保証金の金額(30万円)が定められているため、100株買うのに10万円以下という安い銘柄でも、つなぎ売りをするためには最低30万円(現物株の評価額でも可)は必要です。
つなぎ売りの手数料やコストはどのくらいかかる?
でも、つなぎ売りをするときにかかる手数料などのコストってどのくらいかかるのかちょっと気になりますよね。
つなぎ売りをするときのコストは「現物買いの手数料」「信用売りの手数料」と「貸株料」があります。
- 現物買いの手数料
- 信用売りの手数料
- 貸株料(信用売りの株を借りている間の利息のようなもの)
の3つです。一般信用取引ではなく制度信用取引でつなぎ売りをすると逆日歩がかかることがありますが、これはリスクを考えて基本的にやらないほうが良いのでここでは考えません。
※配当金がある場合は配当金の税金(現物保有分で配当金を受け取り、信用売り分の配当金を支払う、受け取り分は源泉徴収税20.315%の税金を引かれた約80%の配当を受け取り、信用売り分は100%の配当額を払うので税金分の損失が発生する)がありますが、損益通算できる(特定口座・源泉徴収あり+配当受入ありなら口座内で自動的に損益通算されて翌年1月に還付される、他の口座の場合でも確定申告すれば還付される)のでここでは考えません。
現物買いと信用売りの手数料
手数料は株を買うときと売るときの手数料で、つなぎ売りの場合は現物買いと信用売りの2つのポジションを持つため両方の分の手数料がかかります。(参考:ネット証券の手数料比較)
手数料に関しては手数料無料の証券会社を使えば100株なら買いも売りもゼロにできるところも多いですね。
貸株料
貸株料は、信用取引で空売りをしたときに毎日かかるコストです。空売りするときは証券会社から株を借りて売りのポジションを持つことになります。株を借りているからその利息を支払うイメージです。
貸株料は年率なので、1日あたりの金額は株価×100×貸株料率を365日で割って計算します。参考までに貸株料3.9%の場合の1日当たりの金額は以下の通りです。
- 100万円(1万円×100株) 約107円
- 50万円(5000円×100株) 約53円
- 10万円(1000円×100株) 約11円
権利付最終日に買って翌日に売ったら2日分の貸株料がかかります。(※権利付最終日が金曜日の場合は、最短で売っても月曜日までの4日分の貸株料が必要です)
つなぎ売りコスト計算のシミュレーション
貸株料は銘柄によって違うのですが、おおよその目安として、株主優待が人気のマクドナルドをSBI証券でつなぎ売りした場合でシミュレーションをしてみましょう。
マクドナルドの株価は5240円(2021年9月28日の終値で計算)、単元は100株なので必要資金は524000円、これに空売りの資金も必要ですが、信用取引は資金の約3倍の取引ができ、現物株式も担保になるので約55万円で足りますね。
SBI証券の手数料はこの金額だと現物535円、信用385円の合計920円ですが、アクティブプランだと現物も信用も手数料は0円です。貸株料は3.9%なので1日あたり約56円、56円×2日で計算すると112円。
SBI証券のアクティブプランなら112円のコストで株価変動のリスクなくマクドナルドの株主優待が手に入ることになりますね。
株主優待の価値は注文する商品によりますが、1シート700円として700円×6シートは4200円とすると、4000円以上得する計算です。
- スタンダードプランでのコスト 1032円
- アクティブプランでのコスト 112円
同じ計算で、もっと株価の安い吉野家の優待(3000円相当)は48円のコストで手に入ります(株価2240円で計算)。
- スタンダードプランでのコスト 521円
- アクティブプランでのコスト 48円
手数料プランの違いでこれだけ取得コストを下げることができます。
つなぎ売りのコストを下げる5つのポイント
つなぎ売りをするとき、コストがかかりすぎるとせっかく株主優待をもらってもあまりお得でないのでは意味がありません。そこでつなぎ売りをするときのコストを下げるポイントをお話します。
1.手数料の安い証券会社を使う
つなぎ売りでは買い(現物)と売り(信用)の手数料がかかるので、手数料が高いとお得度が減ってしまいます。なるべく手数料の安い証券会社や手数料無料の証券会社を使うことでコストを下げましょう。
SBI証券は、現物・信用それぞれ1日100万円ずつ手数料無料のプランがあるのでつなぎ売りにはおすすめです。
楽天証券やauカブコム証券なども1日100万円まで無料ですが、現物と信用の合算で計算なので、買いと売りの両建てをするつなぎ売りだと50万円分(株価5000円まで)しか枠がありません。
■100万円(株価1万円)まで手数料無料でつなぎ売りができる(現物100万円・信用100万円まで無料)
■50万円(株価5000円)まで手数料無料でつなぎ売りができる(現物と信用の合算で100万円まで無料)
- GMOクリック証券
- 楽天証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- SBIネオトレード証券 ※一般信用売の取扱無し
■25万円(株価2500円)まで手数料無料でつなぎ売りができる(現物と信用の合算で50万円まで無料)
100万円までの無料枠を超えたときの1日200万円までの手数料は以下のとおり。(※2023年5月時点の1日定額制の100万円超200万円までの税込手数料)
- SBIネオトレード証券 1100円
- SBI証券 1238円
- 岡三オンライン 1430円
- GMOクリック証券 1238円
- 楽天証券 2200円
- auカブコム証券 2200円
- 松井証券 2200円(※50万円超〜100万円まで1100円)
つなぎ売りできる金額の大きさでも、無料枠を超えてしまったときの手数料で比較しても、つなぎ売りにはSBI証券がおすすめです。
2.一般信用取引を使う(逆日歩を発生させない)
信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の2つがあります。細かい違いはこのページの趣旨(つなぎ売り)から外れるので詳しい説明は省きますが、それぞれ扱える銘柄が違うこと、制度信用取引では「逆日歩(ぎゃくひぶ)」というコストがかかることがあるという違いがあります。
制度信用取引だと逆日歩(調達料のようなコスト)がかかるのでつなぎ売りの際は一般信用取引で売建てをすることがポイントです。
逆日歩は貸株料のように毎日かかるコストですが、料金が決まっている貸株料と違って状況(需給状況)によってコストがかわります。優待や配当が得られる時期は需要が上がって逆日歩も上がることがあり、思わぬコストがかかってしまう可能性があります。
しかも、逆日歩はいくら必要かが実際に分かるのは取引を行った翌営業日なんです。つまり、制度信用の場合は逆日歩がいくらかかるのかが分からない状態で取引するとになります。これはリスクになりますね。
そこで、つなぎ売りの際は一般信用取引で売建てをすることがポイントです。
ただ、一般信用取引で売建てができる銘柄は証券会社ごとに違っているのと、扱い銘柄が少ない証券会社もあります。株主優待が欲しい銘柄が対応していなければ諦めるか逆日歩を払って制度信用取引で空売りをしないといけないのでその分コストがよけいにかかってしまいます。
その点ではSBI証券 や三菱UFJ eスマート証券は一般信用取引の取扱い銘柄が多いのでおすすめです。
3.寄付前に成行で注文する
買いと売りで約定する値段が違うとそこで損益が出てしまうので、寄付前(午前9時前)に成行で注文をしておくと、その日の初値で同じ値段で約定させることができるので損益が発生しません。
4.できるだけ期間を短く
貸株料(株を借りるために払う利息のようなもの)を最小限に抑えるため、権利付最終日の寄付前に買い、権利落ち日に決済してしまうことで保有期間を最短にします。
決済を忘れて長く持ってしまうと貸株料が毎日かかりコストがどんどん上がっていくので、権利落ち日の決済を忘れないように気をつけましょう。
ただし、優待が人気の銘柄は証券会社の在庫が無くなって空売りできなくなってしまいます。そのため権利付最終日の当日ではなくもっと早くつなぎ売りをする必要があり、他のユーザーとの心理戦になります。
5.決済するときは現渡(品渡という場合もあります)で
株主優待の権利を得たら買った株は売って、空売り(株を借りているような状態)していた株は返済するのですが、そのときに買っていた現物株を売ると売りの手数料がかかり、空売りしていた株は同じ銘柄を買って返済するのでそこでも手数料がかかってしまいます。
でもちょっと待って!空売りで借りた株、つなぎ売りの場合は現物で同じ銘柄を買っているから持ってますよね。
現渡は「この株持ってるからこれで返すね」という決済方法です。現渡だと手数料がかからないので決済するときは現渡で行うことでコストを抑えることができます。
1日定額プランの手数料無料の範囲でつなぎ売りをしていて、決済する日に他の株を買ったりする予定が無い場合は、普通に寄付前の成り行き注文でも大丈夫です。
つなぎ売りを使えば安心して株主優待がもらえる
つなぎ売りを使えば株価が下がって損するリスクがなくなるため、安心して株主優待をもらうことができます。
株価が上下するリスクが無いので、手数料など株主優待を得るためにかかるコストは事前に計算すればわかります。「株価が下がって損した」ということが無いので安心ですね。
しかも、最初のほうでも書きましたが株主優待は1日持ち越せばもらえるため、資金は何度も使い回しができます。月末が権利日の会社が多いため、年に12回以上チャンスがあるわけですね。
必要なコストが事前にわかっていれば株価が下がる心配をせずに株主優待がもらえるので、優待目的で株の取引をする方はつなぎ売りを使ってたくさんの株主優待を楽しんでください。
つなぎ売りをするのにおすすめの証券会社
つなぎ売りをするのにどこの証券会社が良いかを考えるには、手数料・一般信用取引の取扱銘柄の多さを考えます。
- 一般信用取引の取扱銘柄の多さ
- 手数料・貸株料
つなぎ売りのコストの項目でも書きましたが、1日100万円まで手数料無料のプランを使えば多くの銘柄は100株単位なら取引手数料は無料にできます。
SBI証券は、現物100万円・信用100万円までと売りと買いのそれぞれ1日100万円ずつ手数料無料のプランがあるのでつなぎ売りにはおすすめです。
- SBI証券
貸株料:短期3.9%、無期限1.1%
楽天証券・auカブコム証券・GMOクリック証券も1日100万円まで無料ですが、現物と信用の合算で100万円なので、買いと売りの両建てをするつなぎ売りだと50万円分(株価5000円まで)とSBI証券の半分しか無料枠がありません。
それでも複数の株主優待をもらいたい場合にはSBI証券の無料枠だけでは収まらない場合もあるので、口座を持っておくとよいと思います。
岡三オンラインとSBIネオトレード証券も手数料無料の枠はありますが、一般信用取引の売建ができない(制度信用だと逆日歩発生の可能性がある)のでおすすめからは除外しています。
ちなみに100万円までの無料枠を超えると1日200万円までの手数料は以下のとおりです。(※2023年5月時点の1日定額制の100万円超200万円までの手数料)
- SBI証券 1238円
- GMOクリック証券 1238円
- 楽天証券 2200円
- auカブコム証券 2200円
つなぎ売りできる金額の大きさでも、無料枠を超えてしまったときの手数料で比較しても、つなぎ売りにはSBI証券がおすすめです。
次に一般信用取引の取扱銘柄の多さも大事です。その点ではSBI証券 や三菱UFJ eスマート証券は一般信用取引の取扱い銘柄が多いのでおすすめです。
昔から株をやっている人の間では「つなぎ売りといえばカブコム」という印象を持っている人も多いくらいです。