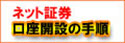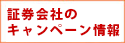空売りのやり方
株式投資では、株価が上がった時に利益を得ることができるのは当然ですが、株価が下がっているときに利益を出す「空売り」(信用売り)というやり方もあります。
株価が下がる場面では損をしてしまうケースが多いですが、下落を予測して空売りをしておけば株価が下がる時でも利益を出すことができるんです。

「これから上がる株を見つけるよりも下がる株を見つける方法が簡単」という空売りのプロもいます。確かに下がる株のほうがわかりやすいですよね。
また、空売りを覚えることによって、株価が上がる時だけではなく、下がるときにも利益を出せるようになれば「利益の出し方の選択肢が増える」ということになります。これは大きなメリットではないでしょうか。
■このページの目次
2022年7月追記:日本株だけでなく、米国株の空売りもできるようになりました。
空売りは信用取引を使って行う
実際に空売りをするときのやり方は信用取引を使って行います。信用取引を使うと自分が持っていない株でも「売る」という取引から始めることができます。
空売りは信用取引でしか行うことができませんので、通常の口座開設をした後に信用取引口座を開設する必要があります。そのため、空売りをするために信用取引口座を開設するという方も多くいます。
- 参考1:信用取引のやり方や信用取引口座開設の手順
- 参考2:ネット証券の口座開設方法
- 参考3:空売りできる銘柄が増えるプレミアム空売り
また、信用取引は通常の現物株取引よりも手数料が安い場合が多く、中には信用取引は取引手数料が無料と言うネット証券(SMBC日興証券の日興イージートレード)もあります。
- 参考:信用取引の手数料比較
信用取引口座を作ったら、「信用売り」という注文をします。「信用売り=カラ売り」です。
現物注文ではなく信用取引の新規取引で、「信用売り」「新規売」など(証券会社によって表記が異なります)で注文を出します。
返済(買い戻し)のしかた
株を買ったら、売って利益が確定するように、空売り(信用売り)をしたら返済(買い戻し)をして利益が確定します。
買った株は売ってはじめて利益確定するのと同じく、空売りで借りて売った株は返済(買い戻し)して利益確定となります。
買い戻し(返済注文)のやり方は2種類あります。
まず、「反対売買」といって、空売りしている株を買って返済する方法です。「返済買い」「返買」など返済のための買い注文をします。こちらが一般的な返済方法ですね。
もう一つは「現渡(げんわたし)」といって、空売りしている株と同じ株を現物で持っている場合に、現物の株で返済する方法です。
証券会社によって画面は異なりますが、基本的には反対売買も現渡も保有株式一覧の画面の銘柄名の横に返済注文へのリンクがあります。
空売りのメリット・デメリット
空売りのメリットは、株価が下落するときにも利益を出せるチャンスがあるというのが一番ですが、これだけではありません。
空売りが使えることによって、ツナギ売りで株価下落リスクを抑えて株主優待を手に入れることができます。
また、現物で持っている株を空売りすることで株価下落リスクを抑えることができます。現物で持って空売りもしているから株価が上がっても下がってもプラスマイナスゼロで持ち続けられます。
「え?持ったまま空売り?なんで?下がりそうなら売ればいいじゃん」と思うかもしれませんが、持っている株を売りたくないケースもあるんですよね。
例えば長期保有株主優待があるから売りたくない銘柄、オリエンタルランドやイオンなどは長期保有株主優待があります。これはもち続けていないと受けられないので、手放したくない人は多いですよね。
また、株主番号が変わって欲しくない場合、例えばイオンの株主優待のオーナーズカードは、最初に届くまで約2ヶ月かかりますが、一度届いた後はそのままずっと継続して使えます。しかし、一度全株を手放して株主番号が変わってしまうとまた新規でカードを受け取らなければいけなくなり、また2ヶ月待つ必要が出てきます。
ソフトバンクグループの携帯電話の割引の株主優待も株主番号が変わらなければ手続きなしで自動継続できますが、株主番号が変わると手続きが必要になりますね。そういった場合にこの方法は使えます。
ただし、空売りしている場合は貸株料(売方金利)という利息のようなコスト(年1%くらいを日割り)がかかり、空売りしている銘柄とタイミングによっては品貸料(逆日歩・ぎゃくひぶ)が発生します。そのため、こういった場合は単元未満株を使う人のほうが多いですね。
空売りのデメリット
当然ですが空売りもメリットばかりでなく、デメリットもあります。
まず、メリットの項目で最後に挙げた貸株料(売方金利)というコスト、そして空売りしている銘柄とタイミングによって発生する品貸料(逆日歩・ぎゃくひぶ)というコスト面でのデメリットです。
また、空売り中に配当落ち日を迎えると、配当金相当額を支払うことになります。
長く持つほどコストも大きくなるのが空売りのデメリットですね。
そして、一番のデメリットは、マイナスの幅が無限だということです。どういうことかというと、通常の取引では一番最悪のケースである「株を買っている企業が倒産」した場合でも、投資した金額以上のマイナスは発生しません。10万円分株を買っていた会社が倒産しても損失は10万円で済みます。
しかし、空売りの場合の最悪のケースは空売りしている企業の倒産ではなく、「空売りしている企業の株価が上がって何倍にもなる」ことです。
株価10万円のときにA株を空売りし、その後株価が急激に大暴騰をして株価が10倍の100万円になったとしたら、100万円するA株を買って返済しなければいけなくなってしまうのです。
とはいっても、信用取引には信用余力というものがあり、「預けた資金の何倍までしか買えない」というルールがあるため、空売りしている企業の株価が上がれば途中で追加資金を入れない限り強制的に返済させられてしまいます。
そのためなかなか「空売りしている株が何倍にも跳ね上がった」なんてことにはなりませんが、例えばストップ高が何日も続いて買い注文が約定しないまま株価が何倍にもなったといったケースも、可能性はかなり低いですがゼロではありません。そうなった場合の損失はかなり大きくなってしまうということです。
例えば少し前に大暴騰したガンホー。大儲けした人がたくさんいましたが、もし空売りしていたら大変なことになっていましたよね。確率的には低くてもそういうケースもあるので注意は必要です。
しかし、逆に2013年6月の高値のときにガンホー株を空売りしていたら・・・翌月7月には10分の1以下まで下がっているので大儲けですね。(あくまで例です。当時ガンホーが空売りできる銘柄だったかは調べていません)
空売りの仕組み
株価が下がるところで利益を出すってどういうこと?と思う方もいるかもしれませんので、どうやって利益を出すのか、空売りの仕組みを簡単に説明します。
株価100万円のA株があります。どうも株価が割高で下がりそうな気がします。そんなとき、証券会社にいくらかのお金を預けておき、それを担保にこの「A株を借りて売る」ことができるんです。
株価100万円でA株を売りました(空売りしました)。そして、A株の株価が80万円に下がったところで、市場からA株を買い戻し、証券会社に返済します。
- A株の株価100万円 → A株を証券会社に借り、市場で売る
- A株の株価 80万円 → A株を市場で買い、証券会社に返済
借りた株を100万円で売り、80万円になったときに買い戻して返済し、差額の20万円が儲けになります。このようなことをするのが「空売り」です。
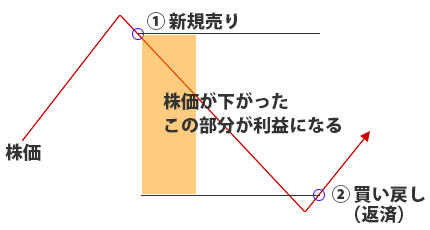
仕組みとしては、証券会社から株を借りて市場で売り、後で株価が安くなったら市場で買い戻して株を返済する、ということになるので、空売りでは株価が下がる局面でも利益を上げられる、というイメージです。
逆指値などを使いリスク管理に慣れてから使う
空売りによる大きな損失も、可能性はかなり低くはありますがゼロではないので注意が必要です。
そこで、空売りをする場合は逆指値注文などを使ったり、損切りラインを決めるなど、リスク管理をしっかりできるように慣れてから始めることをおすすめします。
逆指値などの注文方法をうまく使いリスク管理をしっかりすることで、大きな損失を出すリスクをかなり減らすこともできます。
そして、下落場面でも利益が出せるというのは非常に強いです。
- 「株価が上がる時しか利益を出せない」
- 「上がる時でも下がる時でも利益が出せる」
どちらが有利かは一目瞭然でしょう。
また、ニュースや新聞などの情報を見ていても「この銘柄は上がりそうだな」だけでなく「この銘柄は下がりそうだな」でも”利益を出せる銘柄の候補”になるんです。
利益を出す”選択肢”としてのこの差はかなり大きいですよね。まずは逆指値などを使い慣れて、あなた自身の投資レベルを上げたら空売りも検討してみてはいかがでしょうか。
↑「空売りのやり方がわかった」という方はぜひシェアやいいねで教えてください。