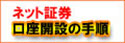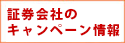SBI証券と楽天証券はどっちがいいの?初心者目線で違いを比較してみました

証券会社の2強と言われるSBI証券と楽天証券。いずれも口座数は1000万口座を超えていて、大手証券会社の野村證券(約540万口座)を大きく引き離しています。(※2024年2月28日時点、SBI証券はグループの口座数、野村證券は残あり口座数)
「SBI証券と楽天証券はどっちがいいの?」
と、この2択で聞かれることも多くなってきたので、初心者目線でSBI証券と楽天証券の違いや選ぶポイントを比較してみました
まずは前提として、手数料などの証券会社を選ぶ大事なポイントだけど両社とも同じものを共有したあとに、両者の違いを解説していきます。
■このページの内容
- SBI証券と楽天証券でほぼ同じもの
- 違う部分(選ぶ決め手になりそうなもの)
・25歳以下か?
・ポイント投資をしたいか?
・外国株を買いたいか?
・株主優待のツナギ売りをしたいか?
・IPO抽選を狙うか?
SBI証券と楽天証券でほぼ同じもの
SBI証券と楽天証券はトップ争いをしているため、証券会社選びで多くの人が重要視するポイントで両社ともほぼ同じというものがけっこうあります。
- 手数料(取引ごとプラン・両社同じ)
(※1日定額プランはSBI証券が有利) - 日本株の取扱銘柄数(両社同じ)
- 米国株の取扱銘柄数(ほぼ同じ・約4200)
- 投資信託の取扱銘柄数(ほぼ同じ・約2600)
- ノーロード投資信託の取扱銘柄数(ほぼ同じ・約2600)
- つみたてNISAの取扱銘柄数(ほぼ同じ・約180)
■手数料無料プラン
手数料は両者ともに手数料無料のプランがあり、国内株式や単元未満株を手数料無料で購入できます。
手数料無料のプランの適用条件は、SBI証券は電子交付サービスの申込、楽天証券はRクロスRとSOR利用です。
取引ごとプランの手数料はSBI証券と楽天証券の手数料は同じです。
■取引ごとプランの手数料比較
| ←表は左右に動かせます← | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 超割コース |
55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
| SBI証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 |
※2023年5月10日時点
電子交付サービス申込済1日定額プランの場合は両社とも1日100万円まで無料なのは同じですが、100万円を超えたときの手数料がSBI証券のほうが安いです。
| ←表は左右に動かせます← | 100万円以下 | 〜200万円 | 〜300万円 | 以降100万円ごと |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0円 | 1238円 | 1691円 | +295円 |
| 楽天証券 | 0円 | 2200円 | 3300円 | +1100円 |
※2023年5月10日時点
また1日100万円の計算もSBI証券は現物と信用それぞれ100万円まで無料なのに対して楽天証券は現物と信用の合計で計算なので、SBI証券のほうが有利です。
1日で100万円を超えるような取引はしないという人なら両社の手数料はどちらのプランを選んでも同じです。
投資信託の取扱銘柄数(SBI証券2637、楽天証券2673)、米国株の取扱銘柄数(SBI証券4194、楽天証券4299)などはほぼ同じです。※2021年10月15日時点
ほぼ同じというのは、多少違うけどユーザーの私たちにとって気になる違いではないというものです。
例えば米国株の取扱銘柄数の違いは若干の違いはあるものの、4000銘柄以上取扱していて差は100程度だと、よほどマイナーなもの以外はほぼ同じで、ユーザーの私たちにとっては大きな差にはなりません。(両社にとっては「取扱銘柄数No1」と言えるかどうかで大きな差かもしれませんが)
でも、ここがほぼ同じだと知っておかないと、両者の違う部分を知ったところで「でも手数料は?」「買える商品が少ないんじゃない?」と気になってしまうので先に共有しておきました。
次からが本題、SBI証券にするか楽天証券にするかを選ぶ決め手になる違いについてです。
SBI証券と楽天証券の違う部分(選ぶ決め手になりそうなもの)
SBI証券と楽天証券の違う部分で、どちらがいいかを選ぶ決め手になりそうなポイントは以下の部分です。
どこを重視するかは人によるので、この中で気になるところを基準にどちらにするかを決めるとよいと思います。
逆にこのあたりに重視する部分がない人は、どっちでも良い(サイトやツールの使い勝手など好みで決めてよい)と思います。
- 25歳以下か?
→SBI証券(25歳以下は手数料無料)
25歳以下の違いを詳しく見る - ポイント投資をしたいか?
→株も投資信託も買えるのは楽天証券、SBI証券は投資信託だけ
→楽天ポイントなら楽天証券、TポイントならSBI証券
ポイント投資の違いを詳しく見る - 外国株を買いたいか?
→SBI証券が有利(OCO注文が使える)
外国株の違いを詳しく見る - 株主優待のツナギ売りをしたいか?
→SBI証券(手数料無料枠が大きい)
→楽天証券も持っておくと無料枠が増える
ツナギ売りの違いを詳しく見る - IPO抽選を狙うか?
→両方作る(両方から申し込んだほうがチャンス大きい)
IPO抽選の違いを詳しく見る
公式サイトへのリンクです。無料で口座開設できます。
あくまで今の時点で気になるポイントでいいいです。今後「やっぱりこれをしたい」となったら、そのときにまた口座を作ればいいだけです。
口座開設は無料だし、口座を作ったけど使わなくても何も問題はないので、両方作って使い比べてみるというのもアリですよ。無料の取引ツールが使えたり口座を持ってる人だけが見れる情報があるので、作っておいて損はありません。
使ってみることで「これ便利だな」とか「ここが不便だな」という自分の好みがわかってくるので、そういうのがわかってきたら他にもっと良いところがないか検討してみてもいいと思います。
次に、それぞれの項目を詳しく解説していきます。
25歳以下か?
SBI証券は25歳以下は国内株式の手数料が無料です。これは楽天証券にはないので、25歳以下の人にとっては大きなメリットです。
ポイント投資の違い
ポイント投資をしたい場合は、「どのポイントか」「何を買いたいか」で選択肢が違います。
楽天ポイントなら楽天証券、TポイントならSBI証券になります。その他のポイントはポイント投資のページを参考にしてください。
また楽天証券は楽天ポイントで株も投資信託も買えるのですが、SBI証券はTポイントで買えるのは投資信託だけです。
これからポイントを貯める場合は楽天ポイントがおすすめです。楽天ポイントは楽天カードで決済額の1%が貯まります(通常のクレジットカードは0.5%なので倍貯まります)。携帯電話や光熱費など毎月必ず使うものを楽天カード払いにするだけでけっこう貯まります。
楽天カード(年会費無料・入会ポイントもあります)
外国株の違い
外国株を買いたい場合はSBI証券が有利です。例えばアメリカの上場企業の株が買える米国株は時差の関係でむこうの取引時間は日本では深夜になります。
そこで、逆指値やOCO・IFDなどの「株価がこうなったら買う(売る)」という条件付き注文を使うのが有効なのですが、楽天証券は米国株の注文でOCOとIFDが使えません。(2023年5月11日時点)
もし、米国株が買いたくてSBI証券か楽天証券にこだわらないなら、トレールストップ注文が使えるマネックス証券がおすすめです。
株主優待のツナギ売りの違い
株主優待を株価が下がるリスクなくもらえるつなぎ売り。つなぎ売りをする場合、SBI証券も楽天証券も手数料プランを1日定額プランにすれば、1日の約定代金100万円まで無料なので、ある程度の約定代金までは手数料無料でつなぎ売りができます。
ただ、1日100万円まで無料の計算がSBI証券は現物取引100万円・信用取引も100万円なのに対し、楽天証券は現物と信用の合計で100万円です。
つなぎ売りは現物の買いと信用の売りを同時に行うため、つなぎ売りで考えた場合の無料枠はSBI証券100万円、楽天証券50万円になります。
SBI証券と楽天証券の両方の口座を持っていれば合わせて1日150万円まで手数料無料でつなぎ売りができるので両方の口座を作るのもおすすめです。詳しくはつなぎ売りでおすすめの証券会社を参考にしてください。
IPO抽選の違い
IPO抽選を狙う場合は、IPOの当選確率を上げる方法で詳しく解説していますが、複数の証券会社から抽選に参加するのがおすすめなので、SBI証券と楽天証券両方の口座を作った方がよいです。(他にもマネックス証券なども作った方が有利です)
ただ、抽選方法の違いがあってSBI証券は抽選もお金持ちが有利なので、SBI証券が主幹事のときはSBI証券から、それ以外のときは楽天証券から申し込むのがおすすめです。
2社に分けるほど資金の余裕がない場合は、SBI証券か楽天証券かにこだわらずマネックス証券がおすすめです(参考:IPOに有利な証券会社)。
SBI証券の口座開設の手順を見る >
楽天証券の口座開設の手順を見る >