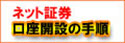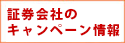NISA(ニーサ)をわかりやすく説明して!
 NISA(ニーサ)について銀行や証券会社の案内をよく見かけるようになり、銀行の窓口や証券会社でもよく見かけます。
NISA(ニーサ)について銀行や証券会社の案内をよく見かけるようになり、銀行の窓口や証券会社でもよく見かけます。
「税金がかからない」と言われて、なんだかメリットがありそうだけど、でも、わかりにくい!
- 「5年?10年?どっちなの?」
- 「毎年120万円が10年なのに最大600万円?」
- 「いったいどういうこと?」
というかたも多いのではないでしょうか。
何となく説明を聞いて、良さそうな気はするんだけど・・・でもイマイチよくわからない、そんな方に向けてニーサを解説していきます。(※「全く初めて聞く」という方はNISAの解説をまず読んでみてください)
■このページの内容
- NISA(ニーサ)の制度の意味がわかりにくい理由
・1.非課税について
・2.非課税枠の計算と期限について
・3.非課税の期限は5年間 - NISA(ニーサ)を簡単にまとめると
- NISA口座の開設はどこでするのがおすすめ?
- ニーサ(NISA)の口座開設の前の注意点
※「つみたてNISAとNISAの違いがよくわからない」という方はつみたてNISAとNISAの違いのページを読んでください。
NISA(ニーサ)の制度の意味がわかりにくい理由
NISA(ニーサ)の制度は「税金がかからない」という部分はわかっても、その他の細かい部分がわかりにくいですよね。
年間120万円までとか最大600万円とか、5年間とか10年間とか、いろいろ混乱しますよね。
一気に考えると混乱するので順番に考えましょう。
1.非課税について
まず、ニーサでは元本120万円までの投資に対しての利益は非課税となります。(通常だと利益から20%の税金を引かれます)
例えば通常なら100万円で買った銘柄が300万円になった場合、利益200万円に対して税金は20%の40万円引かれるので、元本の100万円と税引後利益の160万円の合計で手元に残るのは260万円、利益は160万円です。
でも、それがNISA口座での取引なら税金が引かれないため300万円まるまる手元に残り、利益は200万円になります。
NISAでは元本120万円までを元手にしたものなら、配当金をいくらもらっても、株価が何倍になっても税金を引かれずにそのままあなたの懐に入ってきます。
Point
・元本の合計120万円以内の非課税枠
・そこで出した利益や配当金には税金がかからない
ここまでは理解できましたか?次は非課税枠の計算と使える期限についてです。
2.非課税枠の計算と期限について
ニーサでは元本120万円までは非課税ですが、買った金額の合計で120万円までになります。そしてその非課税枠が使えるのは1年間です。
1年間の間なら1回で120万円の銘柄を購入しても、10万円を12回に分けても、50万円と40万円と30万円でも自由です。1月に買ってもいいし12月に買ってもいいです。同じ銘柄でも別の銘柄を買ってもかまいません。
そして、買った銘柄を売ったら終了です。20万円で買って、利益が出たから売ってまた下がって20万円になったから買い戻したら、非課税の枠を40万円(20万円が2回)使ったことになります。
Point
・120万円の非課税枠は”買った金額”でカウント
・買える期限は1年間
じゃあその間に買ったものはずっと非課税なの?というと残念ながら期限があります。次は非課税の期限についてです。
3.非課税の期限は5年間
120万円の元本で運用した分の配当や売却した利益に税金がかからない期間は5年間です。120万円で買った分に対して5年間の配当金、5年間分の値上がりは税金なしになります。
つまり、買ったあと最大5年間は配当や分配金をもらい続けられるし、株価が上がるのを待ち続けることができるんです。
「なんだ元本120万円か。じゃ上がってもたいしたことないでしょ」と思った方も、5年間運用できるなら2倍3倍も夢ではない銘柄も多いでしょう。しかもその間配当や分配金がある場合は非課税でもらい続けることができます。
途中で売ってしまったら5年未満でもそこで終了です。
Point
・売らずに持ち続けていれば5年間運用できる
・5年間は配当も分配金も税金なしでもらい続けられる
・5年間もの長期運用ならかなりの値上がりも期待できる
ここまでOKですか?
元本120万円まで、非課税で運用できる期間は5年間。複雑でよくわからなかった「年間120万円・最大600万円・5年間・10年間」というキーワードのうち「年間120万円」と「5年間」の2つが順番に見ていくと混乱せずにわかってきたのではないでしょうか。
そして、ここからがややこしいところなのですが、今までのところを理解したならちゃんとわかるので続けていきます。残りの「最大600万円」と「10年間」について解説していきます。
年間120万円の非課税枠は、2014年から2023年までの10年間、毎年使うチャンスがあり、最大で5回使えます。
ここもわかりにくいところの一つですね。「2014年から10年間なのになんで最大600万円なの?」ということですが、簡単です。年120万円の非課税枠を「10年間のうち5回使っていいですよ」というだけの話です。
2023年までの10年間のうち、毎年120万円の非課税枠を使うチャンスが与えられ、10回のチャンスのうち5回だけ使えるということですね。
同じ年に2回以上使うことはできませんが、毎年120万円の非課税枠を使えること、そしてそのチャンスを5回まで使うことができるということです。
追記:2024年からは新しい制度のNISAが始まります。これに関してはまた別途記事を書こうと思います。
NISA(ニーサ)を簡単にまとめると
ちょっとこういうまとめ方は専門家には怒られるかもしれませんが、初心者の方がわかりやすいようあえて誤解を恐れずに言ってしまうと
「元手120万円を使って5年以内に出した利益は配当も売買益も税金なしでいいですよ制度」(ただし売ったら終了)
そして、「これを使うチャンスは10回。そのうち5回使えますよ」
ということですね。
いろんな言い方をしましたが、自分にとって一番しっくりくるもので覚えて下さい。
そして、ここまで理解したらNISAの説明もしっかり理解できるのではないでしょうか。
NISAの口座開設に関しては、住民票などが必要になります。詳しくはNISAの口座開設方法を参考にしてください。
今なら口座開設で2000円がもらえるキャンペーンもあります。ここも岡三かんたん発注など初心者でもとても使いやすいので検討の候補に入れてみてはいかがでしょうか?
「これでNISAがわかった」と思えたら、twitterやfacebookなどでシェアやいいねしてください。
NISA口座の開設はどこでするのがおすすめ?
NISAの制度自体やメリットはどこで口座を作っても変わりません。
ただ、銀行と証券会社では買える選択肢が大きく違います。銀行では株やETFを買うことができないし、投資信託の取扱数も証券会社のほうが多いので、証券会社がおすすめです。
ネット証券のマネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・GMOクリック証券の5社は、NISA口座での株式の売買手数料が無料です。
一時的なキャンペーンではなくずっと無料と発表しているので、まずはこの5社のいずれかでNISA口座を検討してみるのはいかがでしょうか。
中でもマネックス証券に関しては、NISA口座での米国株と中国株の買付手数料を全額キャッシュバックしてくれるので、AppleやGoogleなどのアメリカの有名企業の株も実質手数料無料で買うことができます。
もしNISA口座を作るのを急ぐ必要がないなら、いきなりNISA口座ではなく、まずは普通の口座開設をしてみてください。
NISAは1人1口座しか作ることができません。他社への変更は可能ですが手続きはかなり面倒なので、まずはNISAではない普通の証券口座で使い勝手などが自分に合うかためしてみて、「使いやすいな」「ここで良いかな」と思ったところでNISA口座を作ることをおすすめします。
ニーサ(NISA)の口座開設の前の注意点
NISAの口座は1人1口座しか開けず、1度口座開設をしたらその年は他に乗り換えることができません。
そこで、どこで口座開設をするかが重要になるのですが、いきなりNISA口座を作るのではなく、いろいろなネット証券でNISA口座ではない通常の口座開設をしていろいろ使い比べてみること、できれば気に入ったネット証券を見つけて使い慣れてからNISA口座を作ることをおすすめします。
ネット証券は無料で口座開設できますし、口座開設キャンペーンを行っていて口座を作るだけでお得なところもありますよ。
>> ネット証券の口座開設方法を図解で解説
>> ネット証券のキャンペーン情報一覧
関連リンク
- はじめての新NISA入門 新ニーサのメリットや始め方
- NISA(ニーサ)をわかりやすく説明して!
- ネット証券でのNISAの口座開設方法
- ネット証券のNISAキャンペーン情報一覧
- NISA口座でIPO(新規公開株)が買える証券会社
- NISA口座で単元未満株が買える証券会社
- NISA口座で外国株が買える証券会社
- NISA口座で株取引の手数料が無料のネット証券
- NISA(ニーサ)のデメリットに注意!
- NISA口座の解約(廃止)やネット証券への金融機関の変更のやり方
- 銀行から証券会社へNISAの金融機関変更
- 新NISAは未成年は使えない
- つみたてNISAとNISAの違い
- つみたてNISAの枠を年の途中から使い切る方法
- ジュニアNISAの口座の作り方(口座開設の手順・方法)
- ジュニアNISAの払い出し制限が解消
- SBI証券で5歳の子供の口座開設をしてみました